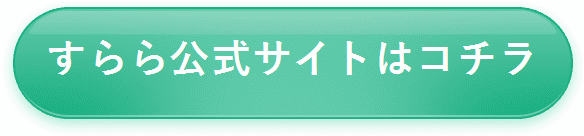すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
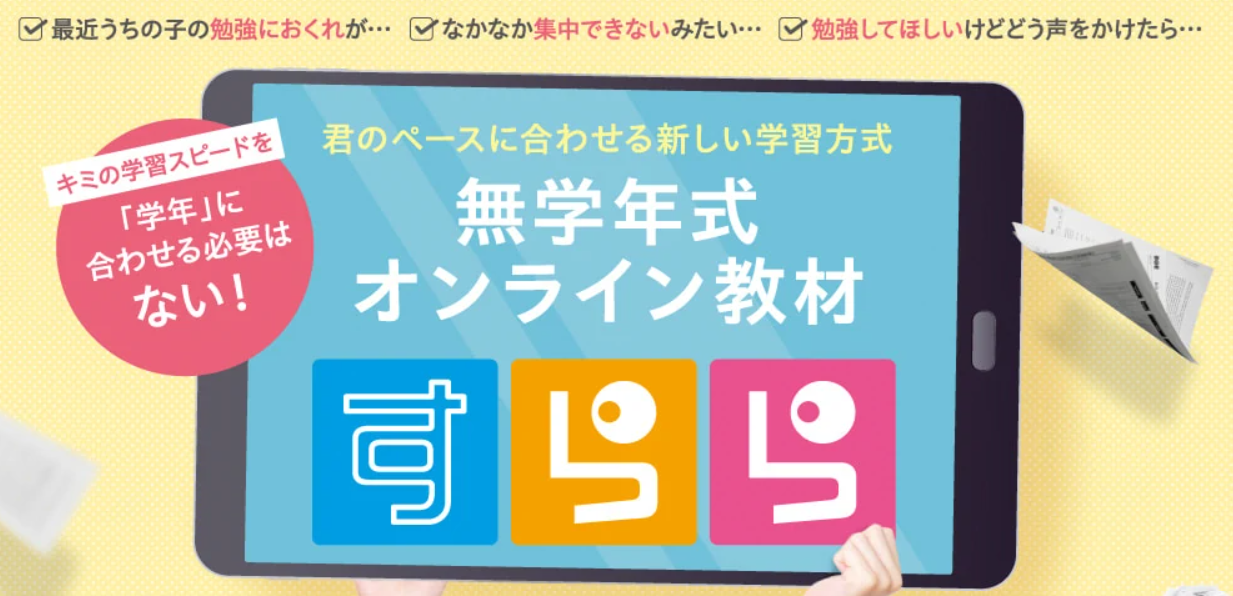
すららは、不登校の子供にとって学びやすいオンライン教材として注目されています。特に、一定の条件を満たせば「出席扱い」として認められるケースもあり、多くの家庭で活用されています。では、なぜすららが出席扱いとして認められやすいのか、その理由を詳しく解説します。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは、ただ学習できるだけでなく、学習の質や進捗状況を客観的に記録できるシステムが整っています。これにより、学校側へ「しっかり学んでいる」という証明がしやすくなり、出席扱いとして認められやすくなるのが特徴です。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、学習の進捗状況や取り組んだ内容を記録する機能があり、そのデータを学校に提出することが可能です。客観的な学習記録があることで、「自宅学習でも十分な学習が行われている」と判断されやすくなります。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
学習記録は自動的に記録されるため、保護者が手作業で管理する必要がありません。学校側もデータを確認しやすく、「しっかり学習していることが証明できる」という安心材料につながります。この点が、出席扱いの認定を受ける際の大きな強みになっています。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
すららでは、単に授業を受けるだけでなく、個々のペースに合わせた学習計画が立てられます。さらに、学習の継続をサポートする体制も整っているため、「計画性」と「継続性」の両面を学校側にアピールしやすいのが特徴です。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららには「すららコーチ」と呼ばれる専任の学習サポートがついており、子供の学習計画をサポートしてくれます。この計画的な学習と継続的な取り組みが、学校側に「しっかり学んでいる」という印象を与えやすくなります。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
専任コーチがいることで、学習計画の作成から進捗管理までをしっかりサポートしてくれます。そのため、自宅学習でも計画的に学べる環境が整い、学習の遅れを防ぐことができます。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
すららは「無学年式」のシステムを採用しているため、理解が追いついていない単元に戻って学習することも、得意な科目を先取りすることも可能です。これにより、学校の授業に復帰した際にもスムーズに適応しやすくなります。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
出席扱いを受けるためには、学校との連携が不可欠です。すららでは、家庭と学校がスムーズに連携できるよう、さまざまなサポートを提供しています。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
出席扱いを申請する際には、学校側に提出する書類が必要になります。すららでは、どのような書類が必要なのか、どのように準備すればよいのかを案内してくれるため、保護者も安心して手続きを進めることができます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
すららでは、学習記録のレポートを作成するためのフォーマットが用意されており、専任コーチが提出のフォローをしてくれます。これにより、学校に対して的確な情報を伝えやすくなり、出席扱いの認定をスムーズに進めることができます。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
学校とのやりとりが不安な場合でも、すららは担任の先生や校長先生との連絡がスムーズに取れるようサポートしてくれます。これにより、家庭だけでなく、学校側とも協力しながら学習を進めることができ、出席扱いの認定を受けやすくなります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、全国の教育委員会や学校と協力しながら、不登校の子どもたちの学習支援を行っています。自治体や教育機関と連携しながら導入が進められているため、信頼性の高い学習ツールとして広く活用されています。学校と同じように学べる環境が整っていることで、不登校の子どもたちが安心して学習を続けることができます。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、文部科学省が推奨する「不登校児童生徒支援」に対応した教材として、多くの学校で導入されています。公式に「不登校支援教材」として認められているため、学校の授業に参加できない子どもたちでも、すららを活用して学びを継続することができます。このような実績があるため、学校側も出席扱いとして認めやすくなっています。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららの学習カリキュラムは、文部科学省の学習指導要領に準拠しており、学校の授業と同じ範囲を学ぶことができます。そのため、学校の授業を受けられない場合でも、すららを利用することで、学習内容に遅れが出にくい仕組みになっています。学校と同じ指導要領に基づいていることで、学びの継続がしやすくなります。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららでは、学習の進捗状況を確認しながら評価を受けることができるシステムが整っています。テスト機能や学習記録があるため、どの程度の理解度があるのかを把握しやすく、必要に応じて復習することも可能です。このような評価とフィードバックの仕組みがあることで、学校側も「学習環境が整っている」と判断しやすく、出席扱いとして認められる可能性が高まります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
すららを活用すれば、不登校の子供でも「出席扱い」として認められる可能性があります。ただし、出席扱いの適用を受けるためには、学校や教育委員会への申請が必要です。申請の流れや必要な書類は各自治体や学校によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。ここでは、出席扱いの申請方法について詳しく説明します。
申請方法1・担任・学校に相談する
まずは、学校の担任の先生や学年主任、校長先生に相談し、出席扱いの申請が可能かどうかを確認します。学校ごとに対応が異なるため、早めに相談することが重要です。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
出席扱いの申請には、学習記録や申請書の提出が必要になることが多いです。また、不登校の理由によっては、医師の診断書が求められることもあります。どのような書類が必要かを事前に学校側と確認し、準備を進めましょう。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
すべてのケースで必要なわけではありませんが、不登校の理由によっては、医師の診断書や意見書の提出を求められることがあります。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
精神的な理由や健康上の問題が関係している場合、診断書を提出することで、学校側がより柔軟に対応しやすくなります。学校の指示に従って、必要な場合は準備を進めましょう。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書が必要な場合、精神科・心療内科・小児科の医師に相談し、「不登校の状態であること」と「学習を継続することが望ましい」という内容を記載してもらうと、学校側の理解を得やすくなります。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららでの学習の記録は、出席扱い申請の際に重要な証拠となります。定期的に学習進捗を記録し、必要な書類を整えて提出しましょう。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららには、学習の進捗状況を確認できるレポート機能があります。このレポートをダウンロードし、担任の先生や校長先生に提出することで、学習の証明ができます。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
出席扱いの申請書は、学校が作成する場合が多いですが、保護者がサポートすることも求められます。必要に応じて、家庭での学習状況を詳しく説明し、学校側と協力しながら申請を進めましょう。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
学校側での手続きが完了すると、最終的な承認が行われます。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
学校長の判断によって、出席扱いの可否が決まります。学習記録や医師の診断書(必要な場合)など、しっかりとした証拠を提出することで、認められる可能性が高くなります。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては、教育委員会に対しても申請が必要な場合があります。この場合、学校側と連携しながら手続きを進めることが大切です。学校側の協力を得ることで、スムーズに申請を進めることができます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
すららを活用して出席扱いを認めてもらうことで、さまざまなメリットがあります。不登校が続くと「学習の遅れ」や「進学への影響」などの不安を感じることもありますが、出席扱いになることで、それらの心配を軽減することができます。ここでは、出席扱いを認めてもらうことで得られるメリットについて詳しく紹介します。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
学校の出席日数は、内申点の評価に大きく影響します。出席扱いとして認められれば、長期欠席とみなされることがなくなり、内申点の悪化を防ぐことができます。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
中学校や高校では、出席日数が少ないと内申点が下がる可能性があります。しかし、すららを活用して学習を続け、出席扱いとして認められれば、出席日数がカウントされ、内申点の評価が大きく下がるのを防ぐことができます。
中学・高校進学の選択肢が広がる
内申点は、高校や大学の進学に影響を与える重要な要素です。出席扱いになることで、欠席日数によるハンデを減らし、進学の選択肢を広げることができます。将来的な進路を考える上でも、出席扱いの制度を活用することは大きなメリットとなります。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校が続くと、「授業についていけなくなるのでは?」と不安を感じることがあります。すららを活用することで、継続的に学習を進めることができ、学習の遅れを気にすることなく、自分のペースで勉強を続けることができます。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららは「無学年式」のカリキュラムを採用しているため、今の学年の授業にとらわれず、自分の理解度に応じて学習を進めることができます。途中で学習の遅れを感じても、必要な単元に戻って学び直すことができるため、「取り戻せない」という焦りを感じることなく、落ち着いて学習を続けることができます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
不登校が長引くと、勉強が遅れていることを理由に自己肯定感が下がってしまうこともあります。しかし、すららを活用して学習を継続することで、「できることが増えている」という実感を持ちやすくなり、自信を取り戻すきっかけにもなります。出席扱いが認められることで「自分はちゃんと学んでいる」という安心感も生まれ、前向きな気持ちで学習を続けることができます。
メリット3・親の心の負担が減る
子供が不登校になると、保護者も「どうサポートすればいいのか」「このまま学習が遅れてしまわないか」と悩むことが多くなります。すららを活用して出席扱いが認められることで、親の心の負担も軽減され、安心して子供を見守ることができるようになります。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららには「すららコーチ」という学習サポートの仕組みがあり、子供の学習を継続的にフォローしてくれます。学校・家庭・すららコーチが連携することで、保護者がすべてを管理しなくても、子供の学習を支える仕組みが整います。そのため、親が「どうすればいいのか分からない」と一人で悩む必要がなくなり、安心して子供の学びをサポートできるようになります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、全国の教育委員会や学校と協力しながら、不登校の子どもたちの学習支援を行っています。自治体や教育機関と連携しながら導入が進められているため、信頼性の高い学習ツールとして広く活用されています。学校と同じように学べる環境が整っていることで、不登校の子どもたちが安心して学習を続けることができます。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、文部科学省が推奨する「不登校児童生徒支援」に対応した教材として、多くの学校で導入されています。公式に「不登校支援教材」として認められているため、学校の授業に参加できない子どもたちでも、すららを活用して学びを継続することができます。このような実績があるため、学校側も出席扱いとして認めやすくなっています。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららの学習カリキュラムは、文部科学省の学習指導要領に準拠しており、学校の授業と同じ範囲を学ぶことができます。そのため、学校の授業を受けられない場合でも、すららを利用することで、学習内容に遅れが出にくい仕組みになっています。学校と同じ指導要領に基づいていることで、学びの継続がしやすくなります。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららでは、学習の進捗状況を確認しながら評価を受けることができるシステムが整っています。テスト機能や学習記録があるため、どの程度の理解度があるのかを把握しやすく、必要に応じて復習することも可能です。このような評価とフィードバックの仕組みがあることで、学校側も「学習環境が整っている」と判断しやすく、出席扱いとして認められる可能性が高まります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、いくつかの重要なポイントがあります。学校や教育委員会によって対応が異なるため、事前に確認し、必要な準備を進めることが大切です。ここでは、出席扱いを申請する際に気をつけるべきポイントについて詳しく紹介します。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いを認めてもらうには、学校側の理解と協力が欠かせません。すららが文部科学省のガイドラインに基づいた教材であることを説明し、学校に納得してもらうことが重要です。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
すららは、文部科学省のガイドラインに準拠した教材ですが、学校側がその点を把握していない場合もあります。そのため、出席扱いを申請する際には、すららが適切な学習教材であることを丁寧に説明し、学校側の理解を得ることが大切です。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
担任の先生だけでなく、教頭先生や校長先生とも相談することで、よりスムーズに話が進みます。学校によっては、出席扱いに関する最終判断を校長が行うケースもあるため、早めに相談しておくと安心です。また、すららの学習内容や活用方法が分かる資料を用意し、一緒に説明することで理解を得やすくなります。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の理由によっては、医師の診断書や意見書の提出を求められることがあります。特に、体調面や精神的な理由で学校に通えない場合は、診断書の内容が重要になることが多いです。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
学校によっては、出席扱いを認めるための条件として、医師の診断書や意見書の提出を求めることがあります。特に、精神的な不調や体調不良が理由で学校に行けない場合は、医師の意見書が申請の際の重要な証拠となります。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書が必要な場合は、かかりつけの小児科や心療内科で相談してみましょう。医師に「出席扱いを申請するために診断書が必要」と伝えることで、適切な書類を用意してもらいやすくなります。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
診断書には、単に「不登校の状態」について書かれるだけでなく、「家庭で学習を継続していること」や「学びへの意欲があること」などが記載されていると、学校側に良い印象を与えやすくなります。医師に相談する際には、すららを活用して学習を続けていることを具体的に伝え、前向きな内容を書いてもらえるようお願いするとよいでしょう。
注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いを認めてもらうためには、学習時間や学習内容が学校の授業に準じたものであることが求められます。単なる自習や短時間の学習では、出席扱いとして認められないこともあるため、注意が必要です。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
すららでの学習が、学校の授業と同等レベルのものであることを示すことが大切です。単に好きな教科だけを学習するのではなく、学校のカリキュラムに沿った学習を進めることで、出席扱いとして認められやすくなります。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
学習時間の目安として、1日2〜3時間程度を確保することが推奨されています。学校の授業時間と大きくかけ離れた短時間の学習だと、出席扱いが認められにくくなるため、できるだけ継続的に学習することを意識しましょう。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
国語・数学・英語といった主要教科だけでなく、理科や社会なども含めたバランスの良い学習を心がけることが重要です。特定の教科だけを学習するのではなく、幅広い内容に取り組むことで、学校側の理解を得やすくなります。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
すららを利用して出席扱いと認めてもらうためには、学校と家庭がしっかり連携することが重要です。多くの学校では、子どもがどのように学習を進めているのかを定期的に報告することを条件としています。学校側に子どもの学習状況を理解してもらうことで、円滑に出席扱いへと進めやすくなります。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららには、学習の進捗状況をまとめたレポートをダウンロードできる機能があります。このレポートを活用し、月に1回程度、学校に提出すると学習の記録をしっかり残せます。学校側も学習状況を把握しやすくなるため、出席扱いの判断をしてもらいやすくなります。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校によっては、学習の様子を確認するために家庭訪問や面談を求められることがあります。こうした機会を活用し、学校側と積極的にコミュニケーションを取ることで、よりスムーズに出席扱いの手続きを進めることができます。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
担任の先生とは、定期的に学習状況を共有することが大切です。メールや電話を活用し、学習の進捗や取り組みの様子を伝えることで、学校との連携がスムーズになります。小さなことでも報告を重ねることで、学校側もサポートしやすくなります。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
出席扱いの判断は、学校だけでなく教育委員会の承認が必要な場合もあります。そのため、学校と相談しながら教育委員会向けの資料を準備し、適切な手続きを進めることが大切です。学校と連携しながら進めることで、スムーズに申請を行うことができます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、いくつかのコツがあります。学校や教育委員会によって判断基準は異なりますが、適切な準備をしておくことで、認められる可能性を高めることができます。ここでは、出席扱いをスムーズに進めるための成功ポイントを紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
学校側が出席扱いの判断をする際、前例があるかどうかが重要なポイントになります。他の学校で出席扱いが認められたケースを紹介することで、学校側の理解を得やすくなります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
すららは、これまでに多くの学校で出席扱いとして認められた実績があります。そのため、他の学校での成功事例を紹介することで、学校側に「前例があるなら大丈夫かもしれない」と安心してもらいやすくなります。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式サイトでは、出席扱いとして認められた事例が紹介されています。これをプリントアウトして持参し、学校側に具体的な実績を示すことで、話がスムーズに進みやすくなります。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
学校が出席扱いを認めるかどうかは、「本人が学習に意欲を持っているか」も大きな判断基準となります。そのため、学習に対する前向きな姿勢をアピールすることが重要です。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
本人が「すららを使ってどんなことを学んでいるのか」「どんな目標を持っているのか」を書いたものを学校に提出すると、学習意欲が伝わりやすくなります。学習の感想や目標を簡単にまとめたノートや手紙を用意すると、学校側の評価も変わることがあります。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
学校との面談がある場合は、可能な限り本人も同席し、どのように学習を進めているかを自分の言葉で伝えるのが効果的です。本人が「頑張っている」と直接話すことで、学校側も安心し、出席扱いを認めてもらいやすくなります。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いを申請する場合、短期間だけ学習しても意味がありません。長く続けられる学習計画を立てることが、認定されるための大切なポイントになります。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
学習の計画は「どれだけ多くの勉強をするか」よりも、「無理なく続けられるか」が重要になります。計画が厳しすぎると途中で挫折してしまう可能性があるため、本人のペースに合わせて進めることが大切です。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららには、学習の進め方をサポートしてくれる「すららコーチ」がいます。コーチに相談すれば、無理のない学習スケジュールを立てることができるので、計画的に学習を進めやすくなります。学校への提出資料としても、具体的な学習計画があると説得力が増します。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
すららを活用する際は、「すららコーチ」のサポートを最大限に活かすことがポイントです。特に、学習証明の提出など、学校とのやり取りに役立つサポートを受けることができます。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
すららコーチは、学習進捗のレポート作成や、学校に提出するための学習証明の準備をサポートしてくれます。学校側が求める書類を整えることで、出席扱いの認定がスムーズに進みやすくなります。すららを活用する際は、コーチのアドバイスを受けながら、適切な準備を進めることが大切です。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
すららは、不登校の子供の学習支援として活用できる教材ですが、出席扱いになる条件や申請方法について疑問を持つ方も多いかもしれません。また、料金やサポート体制についても気になるポイントがたくさんあります。ここでは、すららに関するよくある質問を紹介します。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららに関する口コミの中には、「うざい」といった意見も見られます。その理由として、学習システムの特性やアニメーションを使った授業スタイルが合わないと感じる人がいることが挙げられます。実際の口コミを比較しながら、自分に合った学習方法かどうかを検討するのが大切です。 関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには、発達障害の子供向けに特化した専用コースはありません。しかし、学習の進め方やサポート体制が発達障害のある子供に適しているため、実際に利用している家庭も多いです。料金プランは通常の学習コースと同じで、選択する教科数や契約期間によって異なります。詳細は、関連ページを確認してください。 関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や療育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
すららは、不登校の子供が学習を続けるための教材として活用されており、条件を満たせば出席扱いとして認められる場合があります。ただし、出席扱いの適用には、学校側との相談や必要な申請手続きを行うことが必要です。具体的な申請手順や注意点については、関連ページを参考にしてください。 関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、期間限定のキャンペーンコードが発行されることがあり、入会金の割引や無料体験などの特典を受けることができる場合があります。キャンペーンコードの入手方法や適用の仕方については、関連ページを確認すると詳しく分かります。 関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららの退会手続きは、公式サイトから行うことができます。解約や休会のタイミングによっては、翌月の請求が発生することもあるため、退会を考えている場合は事前に確認しておくと安心です。詳細な手続きについては、関連ページを参考にしてください。 関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららの料金体系はシンプルで、基本的には入会金と月額受講料のみです。ただし、学習に使用するタブレットやパソコンなどの端末は自分で用意する必要があります。追加費用が発生するケースはほとんどありませんが、特別なサポートを希望する場合は、事前に公式サイトの情報を確認しておくとよいでしょう。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららは、1つのアカウントにつき1人の受講が基本となっています。そのため、兄弟で利用する場合は、それぞれのアカウントを契約する必要があります。ただし、家庭の状況によっては特別な対応ができる場合もあるため、詳細についてはすららのサポート窓口に相談するとよいでしょう。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生向けコースには、国語・算数・理科・社会の4教科コースと、英語を含む5教科コースがあります。英語を学びたい場合は、5教科コースを選択することで、小学生向けの英語学習に取り組むことができます。英語のカリキュラム内容や学習方法については、公式サイトで詳しく紹介されています。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららの特徴の一つが、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートの存在です。すららコーチは、学習計画の作成や学習の進め方に関するアドバイスを行い、子供が無理なく学習を継続できるようサポートしてくれます。特に、発達障害や学習障害のある子供の場合は、個々の特性に合わせた学習アドバイスを受けることができるため、安心して取り組める環境が整っています。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
すららは、不登校の子どもでも「出席扱い」として認められる可能性があるオンライン学習教材です。文部科学省が示す「ICTを活用した学習の出席扱い制度」に基づき、すららを活用した学習が学校での出席と同じように認められるケースが増えています。
ただし、出席扱いになるかどうかは、学校や教育委員会の判断によるため、事前に確認しておくことが大切です。また、申請には一定の手続きが必要で、家庭と学校がしっかり連携しながら進めることが求められます。学習状況の共有や定期的な報告を行いながら、適切に進めていくことがポイントです。
ここでは、すららを活用して出席扱いにするための制度の概要、申請の手順、注意点について詳しく解説していきます。